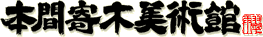箱根寄木細工よくある質問
箱根寄木細工よくある質問

箱根小田原地方で作られる木製品は、「箱根物産」又は「箱根細工」と呼ばれ、さまざまな技術と製品の多さで全国的に有名で、指物技術の「箱根寄木細工」は、その中の一つです。
他に挽物技術の「小田原漆器」「食卓用品」「玩具」等、指物技術の「小箱」「室内用品」等、更に両方の技術を使った多様な「観光みやげ品」等があります。
ここでは、箱根寄木細工についての素朴な疑問をQ&A形式で分かりやすく解説します。
- 質問01 箱根寄木細工はどこの地域で生産されているのですか?
-
箱根町・小田原市が主な生産地です。 (現在では南足柄市で生産している工房もあります)
箱根寄木細工は、日本全国で箱根・小田原地方が唯一の産地です。
箱根町には、畑宿地域(鈴木木工所・浜松屋・金指ウッドクラフト・るちゑ の4工房)と箱根湯本地域(本間木工所 1工房)に工房があります。※箱根町には、この5工房のみしか製造していません。
当工房は、箱根湯本地域にあります。
(小田原市:6工房、南足柄市:1工房)
- 質問02 何人ぐらいで作っているのですか? (2023年6月現在)
-
箱根寄木細工に携わっている職人は、全体で約30~40名だと思われます。(推測値)
そのうち、小田原箱根伝統寄木協同組合に所属している工房は13工房で約25~30名います。
ほとんどの工房が職人1人~3人で多いいところでも5人位だと思われます。
当工房も上記組合に所属しております。
箱根寄木細工の伝統工芸士は6名です。小田原箱根伝統寄木協同組合名簿
伝統工芸士:本間昇・露木清勝・石川一郎・露木和孝・本間博丈・所澤公(認定順) 6名
(箱根寄木細工伝統工芸士会会長:石川一郎)
小田原箱根伝統寄木協同組合:理事長 露木清勝 事務局員:柏木ひろみ
〒250-0055 神奈川県小田原市久野621番地 工芸技術所4F
TEL:0465-32-5252 FAX:0465-32-5253
※当工房は、4人の職人で製作しております。(本間昇・本間博丈・小島勲・村田賢太郎)
※箱根物産連合会名簿・・・小田原地域の木工職人の組合
- 質問03 箱根寄木細工の特徴は何ですか?
-
・日本全国で、箱根・小田原地方のみで作られていること。他の産地では作られていないこと。
・寄木文様は、全て木で出来ていて、色は自然の木の色そのままで出来ていること。
一切、染めたり色を付けたり書いたりしていないこと。
・基本、製作が分業制でなく最初から最後までほぼその工房で製作していること。(一部外部委託有)
・自然の有色材料を寄せ集めてきれいな小さい文様を作り、大きい鉋でスライスしてヅク(経木状)をつくること。
そのヅクを箱類に貼り付けた製品や、無垢の寄木ブロックをそのまま製品にすることで、他の産地にない特殊な製品を作っていることです。
- 質問04 なぜ箱根地方で寄木細工が盛んになったのですか?
-
産地産業が盛んになる理由は、
1.箱根山に多くの種類の材料(木)があること
2.技術があること
3.技術者がいること
が考えられます。
材料である木材は箱根山に昔はたくさんありました。板を組み合わせて、箱や引き出し、たんすなどを作る技術はずいぶん昔からあり、職人さんがこの地方に定住し職人さんの数も増えていきました。
東海道箱根の関所、小田原の宿、箱根温泉のにぎわいもあって、高い技術と特殊なデザインで、みやげ品の箱根細工が盛んに作られるようになり全国的に有名になりました。これが箱根寄木細工が盛んになった理由です。
- 質問05 いつから作っているのですか?
-
江戸時代の後期(約200年前)からで、箱根町畑宿の石川仁兵衛(いしかわ にへえ)という人が創作したと言われています。(※仁兵衛の読み方は、「にへい」ということもあり詳細不明。)
明治時代になって複雑な寄木文様が考案され作られるようになりました。
昭和59年5月に国の伝統的工芸品の指定を受けました。
※当工房は、昭和4年(1929年)創業です。
- 質問06 文様の種類は何種類あるのですか?
-
寄木文様は、およそ50~60種類です。
しかし、色や配置を変えると100種類にも200種類にもなります。
応用のしかたで無限に近い文様が生まれる、不思議な魅力があります。
文様は、日本伝統文様からその工房や職人オリジナルの文様もあります。
基本 幾何学模様となっています。
例えば、麻の葉、市松、矢羽根、青海波、紗綾形、七宝、三枡、などなど
- 質問07 材料の木材はどこから買っているのですか?
-
現在は、日本全国から購入しています。また、外国からも購入しています。
昔は、箱根の山の材料を使っていましたが、今は、国立公園になっているためほとんど使用していません。
当工房では、基本 丸太を購入して製材所で荒木取りして乾燥させ、自分の工房で職人が使用するサイズに細かく木取りをします。
時には、乾燥した材料を購入することもあります。
- 質問08 手作りの良さとは何ですか?
-
自然の木は、同じものがありませんのでそれぞれの木の特性を見て
その都度手で感じて考えて作ることができます。機械では、そうはいきません。
そして、使いやすい大きさ、形、仕組みなど、使う人の便利なように考えながら作られるところが、手作りの良いところです。
- 質問09 箱根寄木細工の作り方で難しいところは何ですか?
-
総合的には、寄木の文様が正確に作られているか、色のバランスがとれているか、
製品そのものがしっかり作られていることです。
文様が正確に作るためには、最初の部材をどれだけ正確に作れているかが大切です。
正確にできていないと模様にズレや隙間が出来てきます。
但し、正確に作れていても寄せる時にズレ・隙間等がないように接着剤で付けていかなければなりませんので
模様を寄せる工程も難しいです。
- 質問10 一人前の職人になるのにどのくらかかりますか?
また、伝統を守るのにどんな努力をしていますか? -
寄木細工の技術を身に着けるには長い年月が必要です。人によって違いますが、およそ10年かかると言われています。
技術を身に着けることは当たり前ですが、いろいろな知識も身に着けないといけません。
例えば、寄木細工の歴史のこと、木のこと、道具のこと、接着剤のこと、箱根の地域のこと、箱根の文化のこと等・・・
また、小田原箱根伝統寄木協同組合では伝統工芸技術や知識を身につける為に研修会を開いたり、
販路拡大、新製品の開発をしたり、地域の行政のご指導のもと振興をはかっています。伝統を守るためには、やはり基本的な伝統の技術を習得すること。そして、それを応用して新しい商品を開発すること。
そして、箱根寄木細工を多くの方に知って頂くこと。
- 質問11 製品はどこで販売されていますか?
-
主に小田原、箱根、伊豆地方のお土産屋さんで売られています。一部、デパートや外国でも販売されています。
直営店(お店)を営業してる工房もあります。
現在では、インターネットでも販売しています。
※当工房でも直営店「寄木ショップ」、ネット店「寄木オンライショップ」で販売しています。
- 質問12 どんな道具を使うのですか?
-
主に、鉋(カンナ)を使用します。他に、鑿(ノミ)、万力(マンリキ)、鋸(ノコギリ)、木型、木綿紐など、
その他自分で工夫した道具などを使います。
現在では、一部機械も使用しています。
- 質問13 製法にはどのようなものがありますか?
-
「貼りの寄木」と「無垢(ムク)の寄木」の2種類があります。
貼りの寄木は、種板(寄木の固まり)を鉋で薄く削って経木状(ヅク)のものを作り表面に貼っています。
貼りの寄木の特徴は、基本模様が細かいということ。寄木細工の源流は、この貼りの寄木になります。
※当工房では「貼り」と記載しておりますが、「張り」とも表記します。
※当工房では「ヅク」と記載しておりますが、「ズク」とも表記します。
無垢の寄木は、種板(寄木の固まり)をそのまま加工して作ります。
その為、どこの面にも寄木の模様が表れます。よって、模様がとても面白く表れてきます。
無垢の製法にも2種類あります。
一つは、寄木の固まりを轆轤などで削りだし製品にします。(例:丸盆、丸茶筒、丸菓子器など)
もう一つは、寄木の固まりを一定の厚みに切って板状にして箱などの製品にします。(文庫、六角茶筒、ペン立てなど)
※当工房では、「貼りの寄木」と「無垢の寄木」と両方の作品を作っています。
- 質問14 どのような商品がありますか?
-
カトラリー系:お箸、箸置き、コースター、楊枝立てなど
箱 系:小さい小箱 から 名刺れサイズの箱、A4サイズの箱、宝石箱など
文 具 系:ボールペン、ペン立て、写真立てなど
テーブルウェア系:ティッシュケース、くず入れ、お皿、茶筒、茶たく、香合、なつめ など
お 盆 系:受皿、トレー、お盆、折敷など
ボール(菓子器)系:菓子器、サラダボールなど
グラス系:ぐいのみ、タンブラーなど
花 瓶 系:花瓶、花立て、一輪挿しなど
引き出し系 :小引き出し
からくり系 :秘密箱(からくり箱)
※箱根寄木細工というと秘密箱が有名です。多くの方が「箱根寄木細工=秘密箱」と思っている方が多いようですが秘密箱は箱根寄木細工の中の一つの商品です。秘密箱を作れる職人は少なく寄木細工職人が全員作れるとは限りません。
※当工房では、秘密箱も製作しております。
- 質問15 接着剤は何を使っているのですか?
-
今は、主に木工用ボンド(酢酸ビニル樹脂系)を使用しています。
※当工房では昭和50年位まで、膠(にかわ)を使用していました。現在は、ほとんど使用していません。
注)膠・・・獣類の骨・皮・腸などを水で煮た液を、かわかし固めたもの。ゼラチンが主成分
- 質問16 表面には何か塗っているのですか?
-
今は、主にポリウレタン塗装を使用しています。
江戸時代、明治時代、大正時代は、漆を塗っていました。漆で塗ると基本淡い茶色の色合いになります。(漆が透明でないため)
昭和初期から昭和50年頃までは、蝋(ロウ)、ニス、ラッカーを塗っていました。
現在は、ポリウレタン塗装を使用しているため、木そのものの色が表現できています。(ポリウレタン塗装が透明のため)
一部ではオイル系の塗装をしている工房もございますので、お買上時にご確認をお願いします。
※当工房では、ほぼ全ての商品に食品安全性のポリウレタン塗装を使用しています。
- 質問17 箱根寄木細工職人になるにはどうしたらいいですか?
-
特に必要な勉強や技術はありません。
箱根寄木細工を教えてくれる学校等もありませんので、基本、工房に入り師匠や先輩達から仕事しながら技術を習得していきます。
その後独立して工房を設立する職人、その工房で仕事を続ける職人もいます。
よって、自分に合う工房(師匠)を探すことです。
- 質問18 箱根寄木細工職人にはどのような資格がありますか?
-
10年以上箱根寄木細工の仕事に従事していれば、「箱根細工技能師」の試験を受けることができます。
※箱根細工技能師は、神奈川県が実施していて、箱根細工の製作に従事する職人の技能レベルを、一定の基準(実技と知識)によって評価する「箱根細工技能審査」を実施し、この技能審査の合格者には、知事から合格証書が交付され、「箱根細工技能師」の称号が付与されます。
12年以上箱根寄木細工の仕事に従事していれば、「伝統工芸士」の試験を受けることができます。
(※但し、箱根細工技能師に合格した者に限る)
※一般財団法人 伝統的工芸品産業振興協会が実施し、経済産業大臣が指定した伝統的工芸品の産地において製造技術のリーダーとして活躍する「伝統工芸士」を認定します。伝統工芸士の試験は、実技・知識・面接試験を行い合格した者に称号が付与されます。
伝統工芸士:本間昇・露木清勝・石川一郎・露木和孝・本間博丈・所澤公(認定順) 6名(2023年6月現在)
- 質問19 箱根寄木細工にはどんな材料を使っているのですか?
-
寄木細工では木材の自然な色合いと木肌が重要です。このため非常に多くの樹種を用いますが、色の系統別による主な木材として、次の種類があります。
【国内産及び外国産の主な用材】
ひらがな・・・国産の木、カタカナ・・・外国産の木、( )・・・以前使用していた木
|